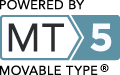昨晩はたまたまテレビをつけた、するとそこに筑紫哲也が立ち戦後60年特別企画「ヒロシマ」なる番組が始まってしばらくした所だった。
戦後60年一言で言うことのたやすさ、自分の認識のつたなさ。
つきなみで、これ以上ないくらい無味乾燥した「戦争」の実感。
さらに、その場でどんなに相容れなくとも、対話がなされることができる、そしてその姿が公開されることによって生まれる、対話の重要な意味がある。
この番組は、そういったとても大切なことを、いくつか教えてくれた。
番組の構成はこうだった。
まず、原爆を日本に投下することを止めるチャンスが、日本にもアメリカにもいくつもあった。
それは、当時の人々の思惑や見込みのあやまりから、つぎつぎと捨てられていく。
次に、とうとう飛び立ったエノラ・ゲイから原爆が投下される、その日の朝の広島の風景。
当時の広島をCGで再現してみせ、さらにその日をいつもの様に過ごそうとしていた人たちの姿を再現してみせた。その日を越えて生き残った人たちの証言をまじえて。
そして、投下され爆発の瞬間。
原爆の内部で核融合の始まりから、爆発、強烈な光と熱線、そして衝撃波。
またたく間に「地獄」にかわった町。
悲惨である、凄惨である。
「やけどの人に水をあげてはいけない」と知りながらも、目の前で苦しみもがく子どもに耐えきれず、水筒の水を一口ふくませてあげてしまい、「ありがとう」といったその直後にその子は息を引き取る。
そんなことをくりかえし、6人の人をみとった男の人の話。
崩れた家からやっとはいだしたものの、いまだ瓦礫のしたにいる我が子を助けられずに火にまかれ、命からがら逃げ延びた母の話。
真っ黒に焼けこげた人を見て、自分が医師でありながら何をしたら良いかわからない状態に、戸惑う軍医の話。
被爆体験の凄まじさを伝える手記の朗読。
この辺りの描写は、今の自分には強烈だった。
はだしのゲンや絵本、広島で平和記念館や原爆ドームを見た記憶。
どこできいたかすら思い出せない、原爆後の光景や戦争の話。
それらがすべて、もし自分だったら、もし自分の子どもだったらと具体的な体験として仮想されていく。
いや、妄想かもしれない。
とにかく涙が出た。悲しかった。この瞬間はアメリカを恨んだほどだった。
なお、番組は進む。
驚いた。
原爆を開発し、投下の瞬間に立ち会い、そして爆発後のキノコ雲を撮影していた博士、アグニュー氏だったか、名前がしっかりと思い出せないが、その人が60年後はじめて日本に来ていたことを放送しはじめた。
彼は、原爆関連の展示品を見てまわり、自分が開発に携わったものや使用していたものには自慢さえ感じささせながら、広島にいた様に見えた。当然だろう、彼にとっては自分が手がけた大きな仕事、ましてやアメリカにとっては原爆はひとつのヒーローとしてあるからだ。
そして、被爆体験者との対談。このようなことが実現していることにも驚いた。
当然の様に、被爆体験者のお二方は「謝罪」を求める、しかし博士にはそれに応じられなかった。
「銃で死のうが、爆弾で死のうが、原爆だろうがそんなことは関係ない。
死ぬときは死ぬし、私も真珠湾で多くの友人を失っている。私は謝らない。」
順番は違うが、もうひとつ大事なことを言った。
「罪のない民間人を、虐殺したのだと言うが、そんなことはない。
戦場にいなくとも、一般市民も何らかのかたちで戦争に貢献しているのだ。」
とても一方的な発言のようだ、聖書を引用した感もある発言だが、間違ってはいない。
自分はそう思う。
この日の対談は、失意のうちにおわっただろう。しかし、この放送には意味があった。
自分の世代が今後の世界を生きる上で、相容れなくとも話をすることで生まれる何かをはっきりと感じた。
「叩かれたら叩き返す」ではない姿。無抵抗ではない最小の抵抗、暴力でない抗力。軍隊でなく、自衛隊でなく、外交そのものが持っている力。
「国単位でも個人単位でも、そういうことが見えるということが大事なのだ」と感じる。
たとえ幾度かの失敗があってもなお。
「リメンバーパールハーバー」と「ノーモアヒロシマ」。
最後に筑紫哲也さんがこういった。
「加害者は被害者の心を理解しにくいという事実がある。日本のアジアへの侵攻、従軍慰安婦問題の様に。
そして戦争には加害者と被害者というものを選り分けにくい性質がある。」
そして「戦争をしない、ということにつきる。」
今から60年前というと1945年。
その年の今日の広島は地獄であった。今この時間には火炎があちこちで暴れ、黒い雨ももう降っただろうか。地獄の中で、生きている人は何をしているのだろうか。